所長コラム
仕事納め
師走に夏日を記録するなど、地球温暖化を肌身で感じた2023年。そんな今年の業務も本日迄となりました。
関係する方々には、大変お世話になりました。大変恐縮ですが、この場を借りてお礼申し上げます。
さて、皆様はこの1年間、どんな年だったでしょうか。あっという間という方もいれば、長かったなぁと感じる方もいらっしゃるでしょう。時の流れの感じ方は人それぞれですが、当センター職員は、全員前者だと断言できます(確認していませんが…)。
というのも、今年は、NPOの果たすべき役割を愚直に探究するという方針のもと、もっと、もっとセンターの業務を前広に打ち出していこう!と積極的に活動を展開することとしました。加えて、人事異動を行い、新規職員を採用して、先例にとらわれず、新たな視点から業務に取り組めるよう職員体制を整えました。結果として、職員一人一人が率先して行動できたのです。
既にご存知の方も多いでしょうが、スピード就職支援、職場定着支援、高次脳機能障がい支援、キャリア相談、ゆらりの会等々、様々なスキームを準備してきました。同時に、相談支援事業所をはじめ、多くの関係機関の方々にお会いして伝えてきました。今後も継続して伝えてまいります。
私たちは、福祉サービスがあるから支援が生まれるのではなくて、解決すべき課題があるから支援というものが生まれ、その手段の一つが福祉サービスであると考えます。それらを具現化するためには、たくさんの方とお会いする必要があります。そして、もっと、もっと当センターの活動を知ってもらえれば、一緒に解決の糸口を見出すことができると確信しています。
2024年は辰年。一説には、これまでの努力(準備)してきたことが、実を結んで成就する年のようです。私たちの思いが叶う年になることを願いつつ、新年を迎えたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします。
アオタイ
例年、この話題に触れていますので、需要の有無に関係なく、またマラソンの話題をつらつらと…。
12月10日(日)、アオタイ(第37回青島太平洋マラソン2023)を走ってきました。いゃー、今年も暑かったです。一昨年のコラムを読み返すと、「暑かった」「セカンドワースト(記録が悪かった)」「出直すしかない(練習不足)」云々…。言い訳のオンパレードだったようです。今年は、それ以上にそうなりそうなので、視点を変えて二言三言。
コロナ禍も明け、今年はマラソン大会も盛んに開催されるようになりました。以前の過熱気味の大会ラッシュには及びませんが、人気が戻りつつあるようです。しかし、場所によっては、運営資金やスタッフ不足によって再開できない大会、無くなってしまう大会もあります。
そんななか2019年に終了した綾照葉樹林マラソン大会が、来年10月に復活するとのこと。全国的に有名な歴史ある大会でしたが、一度終わったものを復活するのは並大抵のことではないでしょう。今の時代に合った楽しい大会になるといいですね。
先進的な大会では、マイボトル、マイカップ携帯、会場周辺のマイカー乗り入れ禁止、エコ素材活用の記念グッズなど、環境面にかなり工夫されているようです。どんな大会になるのでしょうか、ワクワクします。
私たちおじさん世代は、マラソンが真冬の持久走大会の記憶と重なって、「寒くて、辛くて、キツイ」そんなイメージがありました。しかし、昨今のランニング事情はというと、シューズのデザインや性能の向上、有酸素運動の効果、体調や睡眠の改善など、誰にでも取り組みやすいスポーツになっています。それに環境負荷が少ないとなれば、素晴らしいことです。
これからの年末年始は、とかく生活リズムが乱れがち。ダマされたと思って、ウォーキングやジョギング程度から始めてみてはいかがでしょうか。そして、復活する照葉樹林マラソンや各地の大会でお会いできるといいですね。ちなみに、生活訓練の多彩なメニューの1つにジョギングによる体力づくりもあります。一度、お試しあれ。
稼ぐということ
11月ももう終わり、師走はもうすぐ。そして、来春新卒就職の皆さんは、どんな心境なのかと思いつつ、つらつらと…。
就職、就労支援を生業としている立場ですが、今年は、我が家の新卒就職学生を送り出す立場でもあります。
さてさて、我が家の次男くん。就職先から内定を頂き、準備も一段落したのもあって、学校の解禁とともに人生初のアルバイト開始しました。本人曰く、就職までにお金もかかるので、備えたいらしいのですが…。
近所で時給の良い飲食店は、開始初日からフル勤務。それにまずビックリ!。学生なので、平日は配慮して、休日前から休日は戦力にされている様子。帰宅するなり、玄関でバタンキュー!。
本人は言いませんが、1,000円を稼ぐのが、どれくらい大変かということを実感しているのではないでしょうか。私自身、遠い昔の学生時代、当時、時給420円のアルバイトしたおかげで、稼ぐことの大変さを身に付けたなぁ、と今更ながら思い返します。
ここにきて、彼も夜更かしを控え、自然と生活リズムも自立してきているのが分かります。これから、来年3月末までに、運転免許を取ったり、一人暮らしの準備をしたり、転出手続きまでは、多忙な日々が続きそうです。
我が家の話は、これくらいにしますが、いざ、学卒者の皆さんが社会人になるには、様々な準備に加えて、不安も募ることでしょう。そんな不安を少しでも小さくしようということで、来年1月から3月まで『会社デビューを成功させる 社会人準備プログラム』(参加無料)を実施します。近日中にチラシ、ウェブ等でご案内します。是非、問合せいただき、一緒に社会人の一歩を踏み出しましょう。
就活の秋
9月になっても日中30度超ですが、朝晩の風に秋を感じます。そう、就活の季節到来。そんな状況で、つらつらと…。
9月16日から、新規高卒予定者に対する企業選考が始まります。人手不足の中、県内外企業への応募、そして採用はどうなるのでしょうか。
今年は、身近に就活者がいます。就職準備の期間は、2ヶ月程度。その間に、キャリア教育、履歴書作成、面接練習等慌ただしく過ぎていくようです。本人にとっては、相当のプレッシャーでしょうが、一方で社会人になるための貴重な経験です。是非とも乗り切って、採用を勝ち取ってもらいたいところです。
さてさて、就活期間のことについては、前回のブログでもお知らせしましたが、当センター「キャリアアシスト宮崎」では、従来の就労支援に加え、早期(スピード)就職コースという支援を開始しました。これは就職達成の早期目標(期限)を決めて、利用者の方と頑張ろうという取り組みです(詳細はお問合せください)。
6月から広報して、7月から利用された方が内定獲得。9月から開始された方もいらっしゃいます。別に復職支援の方も、丁度2か月で復職できました。
その背景等については、前回のブログに私見を書いています。
ポイントは、『当センターでも、就職後のフォローを手厚くする一方で、多様化する就労支援のニーズに答えていこうという取り組みです。』(前回の抜粋)
つまり、スピード感だと思います。
是非、問合せいただき、一緒に一歩を踏み出してみませんか。
OJT
月1更新を目標にしていますが、7月も末日となりました。そんな状況で、つらつらと…。
当センター「キャリアアシスト宮崎」では、従来の就労支援に加え、早期(スピード)就職コースという支援を開始しました。これは就職達成の早期目標(期限)を決めて、利用者の方と頑張ろうという取り組みです(詳細はお問合せください)。
6月から積極的に広報して、たくさん問い合わせがあります。既に1名がチャレンジ中です。
その背景等について、少し私見を述べます。
そもそも障がいのある、ないにかかわらず、職業準備性のうち、自らが希望する仕事にマッチング出来るかどうかは未知数。経験してみないとわからないという側面もあります。「思っていたよりも…」ということは、良くも悪くもあるようです。
また、転職を考えている場合、キャリアを積みたいという明確な目標もあるでしょう。
今回の取組みは、働く意欲や新しいチャレンジに焦点を当てて、自己理解、仕事理解を深めつつ、早期に求人に応募して採用をつかみ取ろうというものです。
採用としては、トライアル雇用等様々なケースが想定されますが、最も大切なのは、その仕事に適応できることだと考えます。
そこで、採用後は企業と一緒になって初期のOJT(オンザジョブトレーニング、実際の業務を行なう中で必要な知識や技能を身につけること)関わって、職場への適応をフォローしていくことにしています。
精神障がい者の雇用が義務化されて以降、企業からは採用後の継続的なフォローが注目されています。働く障がい者にとっても早期退職は避けたいところです。そういった背景を受けて、当センターでも、就職後のフォローを手厚くする一方で、多様化する就労支援のニーズに答えていこうという取り組みです。
これまで培ってきた支援技法やアセスメント手法を生かしつつ、新しいことにも取り組もうという支援員の意識の高さは、当センターの強みだと思います。
是非、問合せいただき、一緒に一歩を踏み出してみませんか。
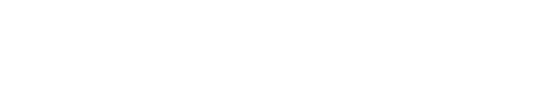
 見学申込み
見学申込み 資料請求
資料請求



 見学申込み
見学申込み
