所長コラム
交流の場
昨日の日曜日、センターでは、予定通り“餅つき大会”を行いました。あいにくの雨模様でしたが、たくさんの方々が参加してくれました。
“餅つき大会”は、初めての企画で、スタッフも不安だったようですが、参加者の皆さんと協力して、大変楽しい時間を過ごすことができました。詳しくは、スタッフブログにアップされますのでお楽しみに。
さてさて、餅つきの様子を眺めながら、思うところをつらつらと…
お餅を食べる機会が多いかどうかや好き嫌いは別として、お餅が食べたいと思えば、スーパーで手軽に手に入れることができます。サ〇ウの切り餅、力うどんのカップ麺、昨席お雑煮等々…。わざわざ餅つきなどしようなんて考えもしないでしょう。
それでは年中行事としてはどうでしょうか。「さぁ、餅つきでもしようか。」と親戚が集うとか最近めっきり耳にしませんし、ましてや臼や杵、蒸し器等々の準備を考えると相当ハードルが上がってしまいます。
私が幼い頃に親に教えられた記憶では、正月前にお餅をつくのは、歳神様にお供えして力を頂くためのもので、鏡開きではそれを分けていただく。たしか、力もちもそこから由来していて、お年玉も昔はお餅だったとか。そして、みんなでお餅をついて準備をすることは、大人から子供までが協力する社会経験だとか。
とはいうものの、核家族化が進み少子化もあって親戚の数も減り、地域の自治活動や子供会活動も希薄になっていると、なかなか思うように社会経験の機会は増えません。それがキッカケかどうかは定かではありませんが、スタッフの発案で開催することに…。
今回は、普段の生活訓練、就労移行カリキュラムでは見れない一面や素晴らしい特性を発見することができ、定着支援を受けている就労者やお友達との交流もありました。つきたてお餅と豚汁でお腹いっぱいになりました。今回のチャンスを逃した皆さん。次の機会には、ぜひ参加されてはいかがでしょうか。
追伸、企画から準備に奔走したスタッフの皆さん、お疲れさまでした。
青島太平洋マラソン2019
昨日、地元のフルマラソン、通称 青太 (アオタイ)を走りました。
ことしで、8回連続エントリー。
『少々寒くても構わないから、晴れるのと風が吹かないで欲しい!』の願いが叶い絶好のコンデション。自身のタイムの良し悪しはさておき、新しい家族の応援もあり楽しんで走れたのが何よりの成果でした。
さてさて、マラソン大会といえば、主役は参加するランナーたち。しかし大会がスムーズに運営されることが前提になります。
全国的にも有名になった本大会は、様々なおもてなしや緊急対応にも力が注がれています。
ランナーからすれば、至極当然なことではありますが、運営がすごく大変なことは、想像に難くありません。そして、それらを末端で支えているのが、4,000人(うち高校生3,000人)のボランティアだということです。ランナーが12,200人なので、単純計算でランナーの約3人に1人の割合でボランティアがいることには驚きです。ありがとうございました。
また、この大会は視覚障害者マラソン宮崎大会も同時開催されていて、大勢のブラインドランナーも走ります。さらに他の障害者の参加もあり、夫々に伴走者がフォローしています。10キロ、3キロレースもありますので、もっともっとたくさんの障害者にも参加して欲しいですね。
自身の記録に一喜一憂する前に、たくさんの人や声援に助けられているのだなぁと、今更ながら考え直した33回大会でした。ということで、来年こそは、コースベストを狙って応援に応える必要があるでしょうね。
コミュニケーション
つぶやきやボヤキは山ほどあれど、なかなか文章にできずに早や3か月。
師走の風の冷たさに焦りを感じつつ、テーマについてつらつらと…。
さてさて、文章を書くことと同様に難しいのが、テーマの(対人)コミュニケーション。いわゆる話して意図を伝えること。いや、伝わること。
先日、子供から私の所有物を貸して欲しいということでかけられたのが、
「〇〇を借りてもいい?」
ん?と私は首をかしげる。
「あっ、ごめん。〇〇貸してもらってもいいですか?」
ん?
「日本語の使い方おかしくない?」と返すと…しばらく考えてから
「〇〇貸してください」
「人にお願いするときは、そう(お願いする)やろうね!」
このやりとりに意地悪な親だと思われるでしょうが、社会に出て誤解を招くのではないかなぁと考えると、つい…
初めの2文。多分、子供としては、相手のことを気遣っての発言でしょうが、一方で聞き手によっては、○○を貸してもらえることを前提にして、その行為に承認をもらいにきたと思われないでしょうか。さらに、自分が傷つかない言い方で、自己中心的だなぁと私は考えてしまいます。
最後のいわゆるお願いは、話し手の借りたいという意思が伝わってきます。ただ、少し大げさですが、貸してもらえないかも!という不安やリスクを感じるのです。つまり何が言いたいかというと、お願いすることで断られることがあることを恐れてはいけないし、交渉することも大切だということ。
日々、支援者として、「報告、連絡、相談」の重要性を伝えていて、これらを習得できるのはもちろんのことですが、これに加えて、自分からお願いすることや援助を求めるスキルも就労定着には大切なことだと日々考えています。実際、些細な誤解から就労継続できなかった残念なケースもあります。
そんなことを思いつつ、子供に接してはいるのですが、件の○○は、持ち主の了解を得ることなく使われていきました。なかなか思うようには伝わらないものです。私のコミュニケーション力不足なのでしょう。
キャリアについて考える
えっ!
気づけば、前回の更新から2か月経っていました。少々夏バテ気味なのは否めないのですが、言い訳はせずテーマについてつらつらと…。
今回は、当センターの事業所名の一つ『キャリアアシスト宮崎』のキャリアについて、少しばかり考えてみましょう。キャリアとは?そしてキャリアアシストとは、どういうことでしょうか?
まず、キャリアの意味を辞書で調べてみると、①専門の仕事や遊びでの経験。経歴。②国家公務員で上級試験に合格している者。ということでしたが、②は別として、①も何となくセンターの業務とは関連付きませんね。
では、キャリアコンサルティング的にはどうかというと、労働政策の権威木村周先生は、「もともとキャリアとは、『何らかの意味で働くことを中核として人生を生きること』である。人生の節目節目で『自分自身を見つめ直し、おかれた環境を精査し、それに適応すること』である。」と述べられています。ふむふむ、人生という長い時間軸も含むことが分かります。
ではでは、当センター的にはどうでしょう。ズバリ、障がいがあっても企業で働くことはもちろんですが、働きながら自ら生活していけることをも含めてキャリアとして捉えています。ですから、先生のおっしゃる後段ところもお手伝いできればというスタンスでいます。もちろん、センターでは請け負えないこともありますし、福祉サービスの範囲内での支援になりますが、様々な機関とのネットワークがありますので、一緒に考えることはできます。
そうすることで、いつでもやり直しができる社会を実現できればという熱い想いを持って、職員は日々奔走しているのでした。
備えあれば患い無しといえども
大雨による被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
昨7月3日は、当地宮崎市も大雨に見舞われ、大荒れの天候となりました。朝はそうでもなかった雨模様も、前日から止むことを知らず降り続け、ついにお昼頃には避難情報が発表されそう。そんな雰囲気を察した主任からの発起で、早速、内部打合せ、情報収集を行いました。結果、13時過ぎには通所利用者の皆さんの帰宅支援を開始し、14時までには帰宅確認を完了させました。
その後、宮崎市全域に避難準備・高齢者等避難開始(レベル3)が発令されたのが、14時30分でしたので、職員一同ホッと胸をなでおろしました。残るは就労中(生活訓練利用)の方の安全確保のみでしたが、これも無事完了。職員も遠方者から順次帰宅して、定時には施設施錠を完了しました。
現在、当センターでは、災害の種別に合わせて4つ(火災・地震、津波、水害・土砂災害、不審者防犯)の対策計画、マニュアルを備えています。しかしながら、それらはあくまでも机上の計画であって(必須ですが)、いざという時に迅速に対応できる事前訓練と発生時の初動が大切です。
昨日から本日にかけての大雨では、職員各人の迅速な行動が功を奏し、関係者は被災することはありませんでした。備えあれば患い無しといえども、人あらずして備えられずといったところでしょうか。
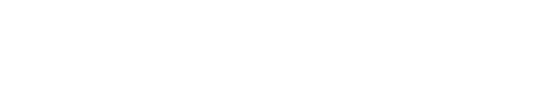
 見学申込み
見学申込み 資料請求
資料請求



 見学申込み
見学申込み
