所長コラム
日南路を走る
久しぶりのブログアップは、やっぱりマラソンの話題だったことは、さておき、太腿の痛みを忘れる前につらつらと…
毎年、秋から翌春にかけてマラソン大会ラッシュだったのを、嘘のように消し去ってしまった憎っくき新型コロナウイルス達。開催中止や延期が相次ぎましたが、少しずつ元に戻りつつあり、人類の英知はスゴイなあと感じます。
さて昨日は、2年ぶり開催された『つわぶきハーフマラソン大会in日南』に参戦してきました。
今年は、県民限定のみのエントリ―で、ハーフマラソンのみ約1000人規模の大会になりました。感染対策として、1週間前からの健康管理観察結果を事前にウェブで申告。もちろん当日も検温に加え、同伴者の名簿を提出、上位入賞者の表彰は郵送等々…
肝心の自身のレース結果は、2年前よりタイムが1分程度落ちたので、練習不足は否めませんでした。しかし、久しぶりに出会う知人達との交流や、なんといっても公道で走ることができることが嬉しくてたまりませんでした。様々なイベントが激減している中で、この大会を開催に踏み切った関係者の方々に感謝しかありません。
ちなみに、この大会は、以前よりおもてなしが厚いということで有名です。今年も大盛りの豚汁(以前はお替りも勧められていました)と地頭鶏の振る舞い、スイトピーの持ち帰りがありました。みなさんもぜひ機会があれば参加してみてはいかがでしょうか。
ただ、難しいなぁと感じたのは、会場内のソーシャルディスタンス。
スタートのウェーブスタート(スタート時間を幾つかに分割する方式)も200人程度になることや、コール後のランナーは疲れていてなかなか思うようにいかないのが現実。大会会長自らが率先して誘導に声出しされていたし…。
一方、紙ベースの記録証がないこと等、そもそもに踏み込んでおられるので、今後の大会も様々に変わって行くのでしょうね。
レース後は、新鮮なカツオを求めて目井津まで足を延ばし、微力ながら地域の経済に貢献させていただきました。
そんなことより、3週間後の青太は、大丈夫なのでしょうか!そこの君!
えっ!私?
リサイクル
身近な二酸化炭素削減について、なるほどと感じたことをつらつらと…
今日、職員のHさんが、1枚のはがきを見せてくれました。
この春、新車を購入したHさん。このはがきは、これまで20余年大切に乗ってきて廃車となった愛車からのお便りでした。
「紫陽花が美しく映える頃ですね。私、愛車のフォレスターです。Hさんお久しぶり!」から始まるこのお便りは、「(中略)、私の部品は色々なところで活躍しています。」と結ばれていました。
ここまででお察しのことでしょうが、地元のオートパーツ店からのお便りでした。
拝見すると、廃車持ち込み後の部品の利用先とCo2削減量が項目別にズラリ!
利用先も国内から海外、製鉄所行まで。Co2削減量の合計は1,165.4㎏だったようです。
なるほど!リサイクルすることから、Co2削減になり地球温暖化防止につながるのだなあ~と、今更ながら気づかされました。
なによりも、これを伝えて下さる企業努力に感心させられたのでした。
ウクレレ
さかのぼること20数年前に出会った、南の島の彼女との出会いとトキメキをつらつらと…
今日は、虫の日だそうですが、“跳ねるノミ”が語源らしい可愛らしい楽器ウクレレ。
出会いの第一印象は、「これがウクレレかぁ~。ちっちゃ!」。
しか~し、独特の弦の並びから奏でられる音色に、すぐに魅了されてしまったのでした。
そのうち自分のウクレレを購入すると、寝る間を惜しんで没頭してしまって、朝起きたらウクレレを抱えたままだったりとか…。家族でドライブ中も弾きたおして迷惑がられるのも日常となり…。ジェイクシマブクロの来日を心待ちにしたり…。上京するとなぜか、別の彼女(ウクレレ)を連れて帰ったり…。現在は彼女も○○本にまでになり…。
今思えば無謀なものですが、当時、仕事が多忙で心も、時間にも余裕が無かったのにバンドの一員に…。そんななかで、とある人との出会いが、大きく視野を広げてくれたのでした。
その方は、「とよちゃん(なぜかそう呼ばれていた)、少しくらい間違えてもいいから、楽しくやりましょう。」「また、上手にかなったなぁ~。」と、素人の私を優しく後押ししてくだいました。実はメンバー不足だったのかもしれない!のは措きますが、良い思い出です。
現在は、そんな活動とは遠ざかっていますが、趣味の一つとして彼女(ウクレレ)とは、長―くお付き合いできています。音楽を楽しめると、少しだけ生活の幅が広がるような気がします。
そうそう、現在、生活訓練の利用者の方で、興味がある方と一緒にウクレレを楽しんでいますよ。土曜日のみの余暇活動ですが、興味のある方は覗いてみませんか?
初鰹
春が近づきつつあるなぁ~と感じながらつらつらと…
今日は、健脚訓練の日。
昨日までの寒さとは打って変わり、風もなく、良く晴れて小春日和の予感。
出発前に所長から一言ということで、「目に青葉 山ほととぎす 初鰹」の一句を紹介。
とても良い季節なので、リフレッシュしておいでと送り出しました。
そう鰹の旬も近いなぁ~。
魚好きで、おおかたの魚は捌けます。きびなごの手開きから鮪の刺身まで。
もちろん食べるのも好きで、鰹が好物。
その中でも、過去に数えるほどしか味わっていない島付きの鰹が美味い!
黒潮に乗って三陸沖を目指さす昇り鰹とは異り、海流の良い島周辺にいる群れらしい。
私が食べたのは、この時期に屋久島あたりで獲れた大型のもの。
刺身を引く柳刃包丁から伝わる肉質の良さ、包丁に張り付く感じからたまらない。
コンビニやスーパーで何でも手に入る飽食の時代。
旬の食べ物をありがたくいただく。
これが私の一番のリフレッシュなのかもしれません。
この原稿を書き終えたお昼前、健脚訓練から無事戻ってこられました。
皆さん笑顔。リフレッシュできたようです。
山は登ってみなけりゃわからない
新年、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
静かに過ごす年末年始が明け、当センターも本日から業務を開始しました。もちろん、これまでの感染対策に加え、在宅支援、個室対応等を行って、「うつらない、うつさない」を徹底しての業務になりました。第三波、変異ウイルス、家族間感染等々、急速な感染拡大への対策を徹底してまいります。関係する皆様には、危機感を共有して頂き、感染対策へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
さてさて、このつぶやきも丸2年が経過しました。初回投稿が2019年1月4日の“はじめまして”。昨年1月7日には“新しい時代への節目”と題し、東京オリンピック後の社会に期待をしてのつぶやきでした。まさか、その1年後がこんなことになっているとは、本当に驚きです。
そんな中、プライベートでは、恒例の年末年始の行事を極力カットせざるを得ませんでしたが、1月2日に尾鈴山(標高1405.2m)に初登りし、山頂の神社にお参りしてきました。もちろん一人で、どこにも寄り道せずに。
尾鈴山山系は、滝が魅力で尾鈴山瀑布群と呼ばれます。最も手軽なのが矢研の滝へのコース。片道30分程度で素晴らしい滝が臨めます。人気は白滝までの滝めぐりコース。白滝までにいくつかの滝を見つつトロッコ道跡の手掘りのトンネルなどが楽しめます。次が尾鈴山山頂コース。登山口までの作業道を4キロ強、1時間程度歩き、登山口から一気に650m昇るためか、ピストンには不人気?(個人的感想です)。
ということで、尾鈴山山頂コースは人も少ないだろうと勝手に決め込んで、10時前にスタート。気温もまずまずで歩いていると気持ち良いくらい。登山口からは汗ばむくらいだったのですが、5合目くらいから急に曇り空に変わり、気温も急降下し始め山頂の温度計は、な、なんとマイナス1℃。最初はそう寒くは感じなかったものの、初詣後にカップ麺をすすろうとするも手がかじかんでうまく食べれない。汗冷えで震えが止まらない。早々に退散(下山)しました。12.2㎞、5時間の山行終了。
ほんと、山は登ってみなけりゃわからない。次回もよろしく尾鈴山。
そんなこんなで始まりました今年も、当センターは、障がい者の社会的自立を多方面からアシストしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
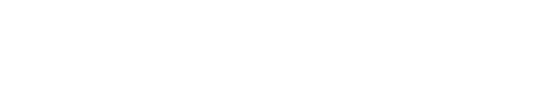
 見学申込み
見学申込み 資料請求
資料請求



 見学申込み
見学申込み
