震災
今回のコラムを書くにあたり、これまでの災害で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
今日、3月11日で東日本大震災の発生から8年を迎えました。テレビ等では、震災後の復興に関する特集が組まれ、復興する被災地の現状と課題を知り、改めて様々な課題を知ることの大切さを感じました。
この震災より遡ること約6年半あまり、新潟県で大きな地震がありました。平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震です。土曜日の夕方に起きたマグニチュード6.8、震度7の地震は、帰宅途中の車をがけ崩れに巻き込みました。数日後に幼い男の子のみが救出された衝撃的な映像が記憶に残っている人も多いと思います。
私は、発生から数日後、被災地へ支援物資を送る拠点確認等のメンバーの一員として現地に入りました。新潟市を基地にして、長岡市を経由して小千谷市に入り、現地自治体を訪れましたが、混乱ぶりは想像を超えていました。被害は甚大で、道路の至る所が崩れ、もしくは寸断されていて立ち尽くしたことを覚えています。その脇には、なぎ倒された電柱や液状化現象で腰の高さくらいまで突き出したマンホールが列を成しています。上越新幹線の脱線した車両などの光景は、今でも鮮明に記憶に残っています。市の体育館前では、自衛隊がお風呂を設営していて、上空にはたくさんのヘリコプターが飛び交っている物物しさから、お年寄りのなかには、戦時中を思い出すと言うほどでした。
当初の任務完了後、ニーズ調査に加わりましたが、住民の方と接していると、そのニーズが刻々と変わっていくことや、被災者の心の変調が直に伝わってくる一方、自身の無力さにも気づかされたのでした。震災支援という経験は、自身のその後の生き方に大きく影響してくることになりました。
現在、おぢやファンクラブの会員として、現地の情報を得たり、特産品を購入することでしか交流はできませんが、近い将来、再び当地を訪れてみたいと考えています。
“非日常に身を置くこと”は、人に様々な影響をもたらすものです。
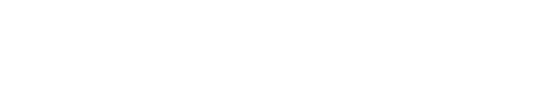
 見学申込み
見学申込み 資料請求
資料請求



 見学申込み
見学申込み

